-
 う御料理「中六」で伊射波伊雜宮ふたつの一の宮と元旅館で5切うなぎ丼まぶしの是非
う御料理「中六」で伊射波伊雜宮ふたつの一の宮と元旅館で5切うなぎ丼まぶしの是非
-
 江戸前「松野寿司」で伝心ひる酒おまかせ寿司小粋なひと時トキワ荘とお祖母ちゃん家
江戸前「松野寿司」で伝心ひる酒おまかせ寿司小粋なひと時トキワ荘とお祖母ちゃん家
-
 鮨「八郎すし」で末廣柳八目勘八赤烏賊万寿貝紺碧卵の甘海老喉黒吉永小百合と梅ノ橋
鮨「八郎すし」で末廣柳八目勘八赤烏賊万寿貝紺碧卵の甘海老喉黒吉永小百合と梅ノ橋
-
 鮨「はしもと」で青柳桜海老茶碗蒸し初鰹蛍烏賊鰯海苔巻春子鯛鮪剥し桜鱒鰆春の握り
鮨「はしもと」で青柳桜海老茶碗蒸し初鰹蛍烏賊鰯海苔巻春子鯛鮪剥し桜鱒鰆春の握り
-
 天麩羅「登良屋」で一人前盛り天麩羅通し営業の白木の角気取らぬ老舗の佇まい
天麩羅「登良屋」で一人前盛り天麩羅通し営業の白木の角気取らぬ老舗の佇まい
-
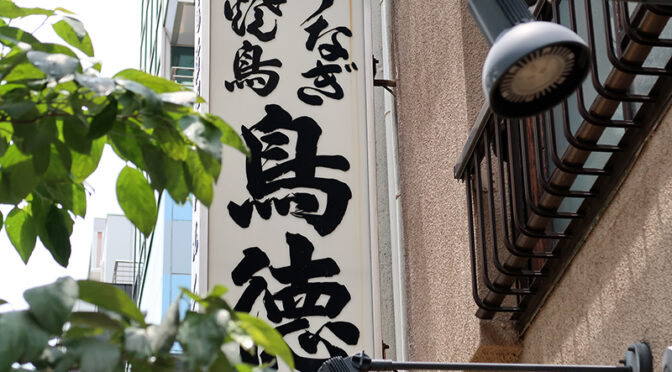 かやば町「鳥徳」で大人気鳥鍋御前特製弁当きじ焼き重飴色の階段昭和の風情がまた
かやば町「鳥徳」で大人気鳥鍋御前特製弁当きじ焼き重飴色の階段昭和の風情がまた
-
 鮨「石島」本店で柚子香るづけ霞ヶ浦の白魚蛍烏賊のスチーム桜の頃のカウンター
鮨「石島」本店で柚子香るづけ霞ヶ浦の白魚蛍烏賊のスチーム桜の頃のカウンター
-
 うなぎ「川勢」でひと通り串焼八幡焼きも焼ひれ焼ばら焼れば焼きも刺えり焼はす焼
うなぎ「川勢」でひと通り串焼八幡焼きも焼ひれ焼ばら焼れば焼きも刺えり焼はす焼
-
 鮨「伊とう」で相模湾地物魚介の肴鮨伊藤家のつぼは今真鶴の粋な佇まいの中に在る
鮨「伊とう」で相模湾地物魚介の肴鮨伊藤家のつぼは今真鶴の粋な佇まいの中に在る
-
 和食「松うら」で一品勝負の天丼の湯気と六月の晦日の夏越ごはん
和食「松うら」で一品勝負の天丼の湯気と六月の晦日の夏越ごはん
-
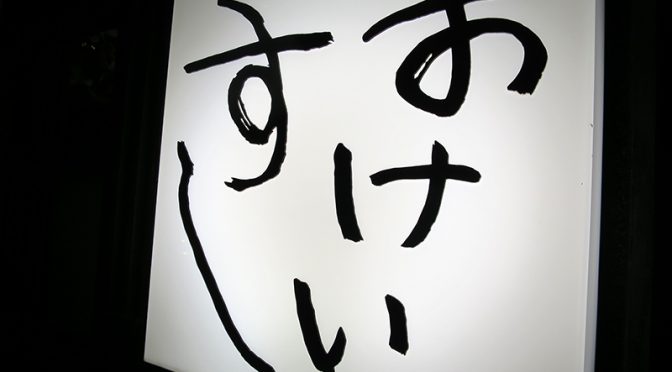 鮨「おけいすし」で丁度一年振りの同じ白木のカウンターに今更乍ら想うこと
鮨「おけいすし」で丁度一年振りの同じ白木のカウンターに今更乍ら想うこと
-
 寿し「福助」で路面電車に薬売りふっと誘われ地魚にぎりサスに八目に白海老に
寿し「福助」で路面電車に薬売りふっと誘われ地魚にぎりサスに八目に白海老に
-
 天ぷら「天房」で天麩羅定食穴子芝海老丼美しき赤身の限定鮪定食もございます
天ぷら「天房」で天麩羅定食穴子芝海老丼美しき赤身の限定鮪定食もございます
-
 うなぎ「ほさかや」で鰻塩焼き串ひと通りレバ酒蒸し自由が丘駅背にした昭和な鰻処
うなぎ「ほさかや」で鰻塩焼き串ひと通りレバ酒蒸し自由が丘駅背にした昭和な鰻処
-
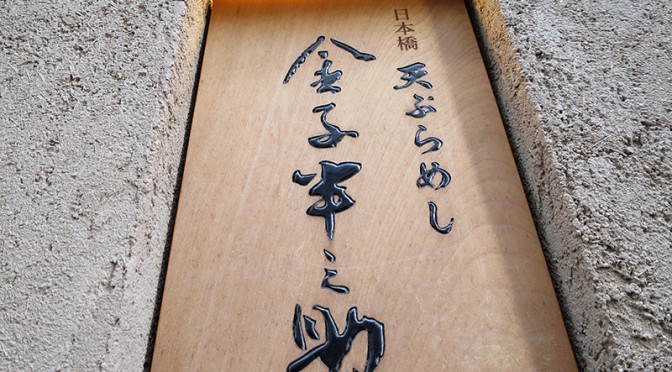 日本橋天ぷらめし「金子半之助」で穴子一本揚げ海老天四本の天麩羅飯悔しい哉
日本橋天ぷらめし「金子半之助」で穴子一本揚げ海老天四本の天麩羅飯悔しい哉
-
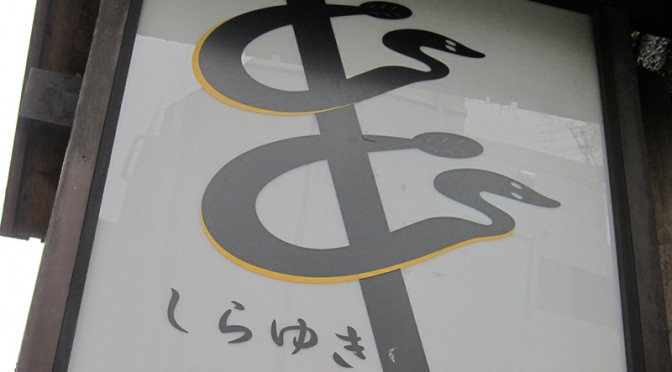 うなぎ「しらゆき」でうなたま丼うな重竹に月見親子丼鰻供するお店の苦慮と
うなぎ「しらゆき」でうなたま丼うな重竹に月見親子丼鰻供するお店の苦慮と
-
 鰻「とみた」で茶漬けにしない櫃まぶし或る夏の日の想いで
鰻「とみた」で茶漬けにしない櫃まぶし或る夏の日の想いで
-
 立喰「栄寿司」で立ち喰い八貫瓶麦酒アーケードの夕陽と束の間の滞在
立喰「栄寿司」で立ち喰い八貫瓶麦酒アーケードの夕陽と束の間の滞在
-
 立喰ずし「津々井」で秋刀魚小肌生牡蠣芽葱山牛蒡気風と紫煙
立喰ずし「津々井」で秋刀魚小肌生牡蠣芽葱山牛蒡気風と紫煙
-
 魚介料理「本種」で 豪快にいこうにぎり寿し1.5丸ちらし鯔背な大将
魚介料理「本種」で 豪快にいこうにぎり寿し1.5丸ちらし鯔背な大将
