 埼玉県南中部の狭山市・入間市に跨って、航空自衛隊の基地、入間基地はある。
埼玉県南中部の狭山市・入間市に跨って、航空自衛隊の基地、入間基地はある。正門を入ってすぐの主要施設の所在からか、所在地は狭山市稲荷山となっている。
入間基地という名称ながら、司令部等を含む敷地の9割が狭山市域にあるらしい。
防衛省のWebページによると、
現在の入間基地の所在地は、
1938年(昭和13年)に旧陸軍の航空士官学校が開設された場所で、
終戦後に進駐したアメリカ軍が「ジョンソン基地」と名付けたことで、
その名前で広く知られるようになったという。
稲荷山公園への花見の帰りがけに訪ねた、
ジョンソンタウンの名もその”ジョンソン”だね、
などと話し乍ら、と或る茶畑の広がる場所へ。
その日は、入間航空祭が催される文化の日。
一般開放される基地内は大混雑必至なので、
基地からはやや離れた場所から、
ブルーインパルスの展示飛行を眺めようと、
やってきたのであります。
ダイヤモンド形の陣形で滑走路方向へ飛びゆく4機。

 雲のかかる空もあるものの、
雲のかかる空もあるものの、
およそ快晴の青空に白い航跡が映える。
隊形で上昇して一気に散開する演目は、
サンライズと呼ばれるもの、らしい。

 5機で星を描く「スタークロス」や、
5機で星を描く「スタークロス」や、
ハートマークをスモークの矢で射貫く、
「バーティカルキューピッド」も見られたけれど、
ちょうど近くの電柱の向こうだった……(^^)。
久々にブルーインパルスを観れたと満足して、
その足でと目論んでいた場所へと向かう。
通称463行政道路を武蔵藤沢駅方面へ車を走らせ、
インデラ・カレーの交叉点を右折する。
 その先の右手に見えてくるのが、
その先の右手に見えてくるのが、
「懐かしのうどん」と書かれた袖看板だ。
スクエアな印象の3階建ての建物は、
全面が萌黄色の個性的なファサード。
 縦格子の上にも横長の看板があって、
縦格子の上にも横長の看板があって、
「三丁目の手打うどん」と表示されている。
「懐かしのうどん」は判るけれど、
「三丁目の手打うどん」とは、
はて、どふいふことでしょう(^^)。
ドアを引き開けて店内に入ると間髪入れずに、
まずはセルフのお冷をどうぞと、
左手にある給水器の案内をいただくのが、
ここでの恒例となっている。
入って左手に厨房に向かう3席のカウンター。
右手には小上がりの板の間があって、
有難いことに炬燵スタイルに、
足を下に降ろせるようになっている。
 その上には彫刻のある和風の座卓が載る。
その上には彫刻のある和風の座卓が載る。
それだけでなんだかなんとなく、
お祖母ちゃん家にいるような気にさせるから、
不思議に面白い(^^)。
板の間からカウンター方向を振り向けば、
天井近くに万国旗状に旗を吊り提げていて、
国産地粉100%と謳っている。
 このことは、武蔵野うどんっ喰いには重要で、
このことは、武蔵野うどんっ喰いには重要で、
それを正々堂々と宣言してくれているなんて、
なんとも頼もしいのであります。
そんなカウンターが向き合う板壁には、
揚げ立て本日の天ぷらと題するパネル。
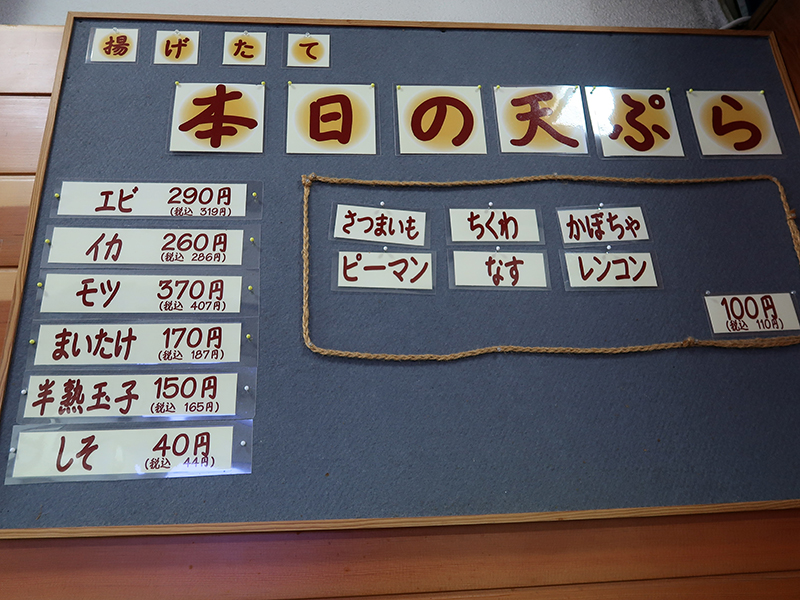 うどんを選ぶに続いて、
うどんを選ぶに続いて、
このパネルから天婦羅を選ぶのが、
ご註文の段取りとなっております。
ぐるっと迷って、やっぱりコレ!となるのが、
「肉つけ麺」並盛でありましょう。

 湯掻き立て〆立てのうどんのその色が、
湯掻き立て〆立てのうどんのその色が、
明らかに茶褐色を帯びているのが判る。
小麦の粒の外皮部分の粒子、
衾が入っている様子はないのに、
この色味ということが地粉をしっかりと、
使っていることの証左のひとつに違いない。
手打ちうどんの証、俗に云う”はじっ娘””みみ”も、
勿論のことうどんに含んでいます。
つけ汁に浮かぶ豚バラ肉は、
ちょうどよい大きさにしてちょうどよい厚み。
「肉つけ麺」=「武蔵野うどん」の醍醐味のひとつが、
豚の脂の滲んだつゆにあるのは周知のところ。

 そんな豚バラ肉とうどんを箸に挟んで啜れば、
そんな豚バラ肉とうどんを箸に挟んで啜れば、
地粉の風味とバラ肉の甘さとつゆの旨味が、
混然と一体となって、唸らせる。
決して麺が硬くなどなく、
加減のいい噛み応えから粉の風味のする。
うんうん、こうでなくっちゃ(^^)。
裏を返すように訪れたおひる時には、
「肉うどん」並盛を豚増しで所望する。

 近隣の精肉店から都度々々仕入れる、
近隣の精肉店から都度々々仕入れる、
新鮮な国産の豚バラ肉がどんぶり一面に広がり、
早よ食べなはれと誘ってくる(^^)。
豚増しが出来るか否かも、
デキる武蔵野うどん店か否かの尺度のひとつだ。
麺も温かい所為か、
麺とつゆの一体感がより強い。
 枕崎産の鰹節、鯖節を使うというつゆは、
枕崎産の鰹節、鯖節を使うというつゆは、
特段の特徴のない代わりに、
シンプルに濁りなく素直に旨い。
そんなつゆにふんだんに、
これまた濁りなく豚の脂が滲んで、
太さも加減のよい地粉の麺と一緒になって、
啜る口腔に飛び込んでくる。
ずるずるずー、ずるずるずー。
うん、うまーーい(^^)。
ちなみに、つけ麺では、小盛、並盛、中盛、大盛が、
かけ麺では、並盛、大盛が選べるようになっています。
豚バラ系が本筋ではあるけれど、
カレー系もやっぱり気になるじゃぁないかと、
ふたたび訪れると、頭上からエンジン音がする。
 青空を仰ぎ見れば、周回する練習機か、
青空を仰ぎ見れば、周回する練習機か、
両翼に日の丸を描いた飛行機が見えた。
今度のご註文は「カレーつけ麺」普通盛り。

 盤石と安定の地粉麺は、この日も勿論茶褐色。
盤石と安定の地粉麺は、この日も勿論茶褐色。
ご提供まで15分ほど時間を要するのは、
註文を受けてから湯掻いて〆てをするから。
その、瑞々しさが見た目からも伝わってくる。
カレーのつけ汁はと云えば、
もはや汁と呼ぶよりは、
ディップとでも呼んでも不思議のない濃密さ。

 そんなカレーに茶褐色のうどんをディップ。
そんなカレーに茶褐色のうどんをディップ。
こりゃカレー味一面だろうと思えば然にあらず、
辛味控えめが嬉しいカレー風味の中から、
地粉の旨味がしっかりと伝わってくる。
いいねぇ、やるねぇ(^^)。
地粉のうどんに合うカレー汁をと考える裡に、
この濃度に辿り着いたんだろうね。
この日の天ぷらの中に、
数量限定で特大の「しいたけ」があった。
 成る程、大きくて肉厚で、
成る程、大きくて肉厚で、
噛めばたっぷりの椎茸の旨味炸裂。
時季時期の限定モノもこれまた嬉しいのぉ。
「カレーつけ麺」がよければ、
「カレーうどん」だってきっと負けてない。

 少々粉チーズを振って、
少々粉チーズを振って、
貝割れを載せるのがデフォルトである模様。
うどんの気配のないカレー汁の中から、
茶褐色の地粉うどんを掬い上げる。
やっぱり、つけ麺よりも一体感が増して、
どちらかと云えば、かけのカレーの方が好み。
そして、やっぱり地粉の風味がしっかりとする。
小麦粉は埼玉県内産か、
はたまた群馬県産あたりでありましょうか。
武蔵藤沢駅方面へ向かう463行政道路から、
インデラ・カレーの交叉点を右折した横道沿いに、
武蔵野うどん「三丁目の手打うどん」は、ある。
 その所在は、埼玉県狭山市水野1266-49。
その所在は、埼玉県狭山市水野1266-49。
三丁目にある訳じゃないのですねと訊けば、
店主田島さんの、
練馬で農家を営む母方のご実家では、
お祖母ちゃんやお母さんがうどんを打っていて、
遊びに行った店主本人もうどんを踏んだりしてた。
そんな経験からか、自宅でもうどんを打ち、
家族で食べていた清瀬のご自宅の住所が三丁目で、
転居した先の東村山のご自宅も偶々三丁目にあった。
そんなことから、三丁目の我が家に立ち寄る感じで、
食べきに来てくれたら、との思いから、
「三丁目の手打うどん」と店の名をつけたという。
この地も三丁目だったらもっとマッチした、かも?
お代を支払っての帰り際には、
お腹一杯になりましたか?はい!というのが、
お決まりのやりとりになっている。
また、お腹空かせてお邪魔しますね(^^)。
「三丁目の手打うどん」
埼玉県狭山市水野1266-49 [Map]
04-2958-3262
https://www.instagram.com/santyoumenoteutiudon/

