 池袋駅のホームを出発した西武池袋線各駅停車が、2分後に辿り着くのが、椎名町駅。
池袋駅のホームを出発した西武池袋線各駅停車が、2分後に辿り着くのが、椎名町駅。駅名はうろ覚えでも、北口駅前に肉そば肉うどんの店「南天」のある駅と聞けば、あっと思い出す方もいる、かもしれない。
椎名町駅の次に各駅停車が停車するのが、東長崎駅。
その東長崎駅の駅名は、
駅開業当時所在していたのが、
鎌倉時代の武将長崎氏が居を構えていたことに由来する、
長崎村であったことがひとつ。
それに加えて、長崎県長崎市所在の長崎駅と区別するために、
「東」を冠したことから、と云われている。
九州の駅と取り違えるひとがいるとは思えないけど、ね(^^)。
そんな東長崎駅は、
特に子供の頃に時折利用した憶えがある。
それは母方のお祖母ちゃん家を訪ねるため。
もうとっくに廃業して、今はもう誰もいないけれど、
千川通り方向から南東方向へ走り、
目白通りへと斜めに合流する南長崎通り沿いで、
米屋を営んでいたのがお祖母ちゃん家だ。
南長崎を通る故、
南長崎通りと呼ばれていた通りが、
2024年の6月に「トキワ荘通り」と改称された。
「トキワ荘」と云えば、ご存じの通り、
手塚治虫をはじめとする、
マンガの巨匠たちが住み集って、
若き青春時代を過ごした伝説のアパート。
現トキワ荘通りの中心的存在と云えば、
それは「豊島区立トキワ荘マンガミュージアム」。
 その昔この場所には、
その昔この場所には、
通りに面して材木店があったことをよく憶えてる。
ミュージアムをゆっくりのんびりと、
時間を遡るように辿れば、
昭和中期にあたる1950年代のアパートの様子と、
そこで暮らし、マンガを書き綴った、
多くの漫画家たちの生き様が、
自ずと浮かび上がってくるよう。
アパートの裏手には、2階の便所から階下へと、
垂直の土管が剥き出しで通じていて、
漫画家たちが用を足す際には、
排泄物が1階のぼっとん式のツボへと落下する。
その時の音が「ガチャーン!」だったってのが、
特に印象的であります(^^)。
ミュージアムを後にして、
退去後もそのままになっている、
かつての米屋の建物を眺めてから、
トキワ荘通りを目白通り方面へ。
夙に知られた町中華「松葉」の前から、
トキワ荘跡地に寄って、碑を読み、
トキワ荘通りを左折して今度は、
トキワ荘通りの北側を並行して、
住宅地を通り抜ける、大和田通りを往く。
通り沿いに何気なく、町鮨然と佇むは、
「松野寿司」の飾りなきファサードだ。
 松葉色というよりは、常盤色という感じの、
松葉色というよりは、常盤色という感じの、
渋く鮮やかな深緑色の暖簾に、
松の紋の大きな白抜きが映える。
テント地の文字の掠れ具合も悪くない。
そんな暖簾を払い、予約の名を告げて、
小さなL字カウンターの一隅へ。
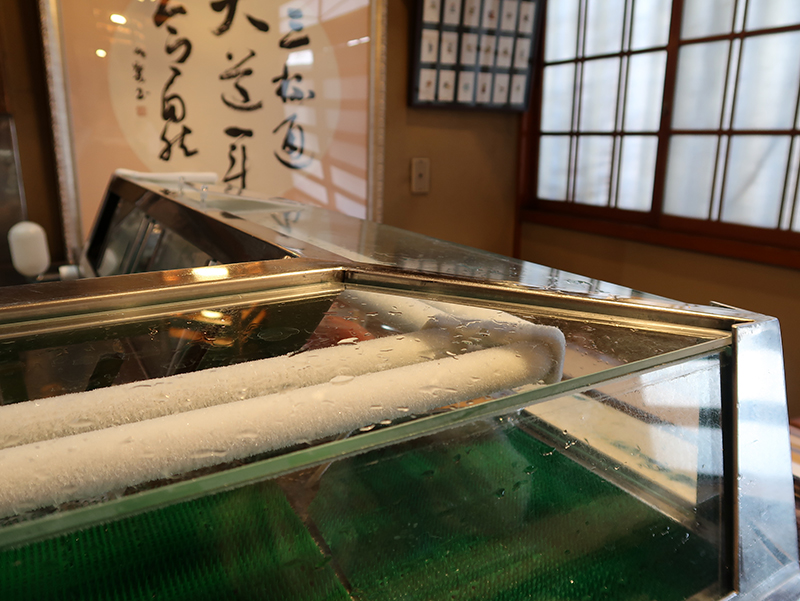 昭和を思わせる硝子ケースの中に、
昭和を思わせる硝子ケースの中に、
霜の付いた冷却管が見付かる。
カウンターに沿うようにL字になっている、
つまりはL字の硝子ケースが現役の店って、
初めてかもしれない。
お邪魔したのは、この三月中旬の日曜日。
おつまみ付のおまかせ寿司をお願いして、
心待ちにしていたひる酒の吟味に入る(^^)。
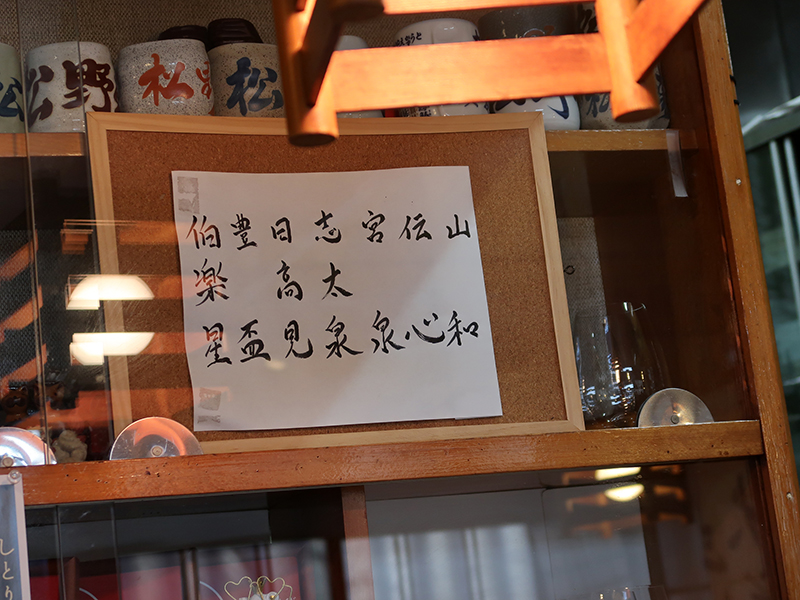 カウンターの脇の硝子棚の中にコルクボードがあり、
カウンターの脇の硝子棚の中にコルクボードがあり、
そこに「日高見」「豊盃」など七つの銘柄が並んでる。
でもね、お酒もおまかせでお願いしましょう。
大将のチョイスは福井の「伝心」。
 この日の陽光にも似合う、
この日の陽光にも似合う、
涼し気な硝子の酒器が、いい。
お通しチックな小鉢には、貝ひも。
 帆立の外套膜、ミミというかヒモというか。
帆立の外套膜、ミミというかヒモというか。
ポン酢で洗ったような感じがして、
冷たくした「伝心」にも似合う、いいつまみだ。
お次のおつまみは、平目。
 食感も脂のノリも全然違う部位を愉しみつつ、
食感も脂のノリも全然違う部位を愉しみつつ、
「伝心」をチビチビっと。
縁側の際なのか、平目にも、
こんな脂たっぷりの場所があるんだね。
そして、鰤。
 香りよく、脂の加減もちょうどいい。
香りよく、脂の加減もちょうどいい。
大き過ぎない、ワラサ寄りの鰤、
と想像したりする。
そこへまた、おかわりした「伝心」を、ね。
三つめのおつまみに、中トロ。
 ひる酒のお供には、
ひる酒のお供には、
これくらいがやっぱりちょうどいい。
ひと皿にまとめてトンと出されずに、
ひとつづつ、間を置いて出してくれる、
そのテンポがいい具合のつまみとさせる、
そんな側面もあるのかもしれません。
ここでの会話は、
お祖母ちゃん家での想ひ出話。
一番に思い出すのは、
訪ねる度に出してくれた「プラッシー」のこと。
今はもう販売を止めてしまったけれど、
米屋との取引があった武田薬品工業が、
米屋を販売窓口として製造販売していたものだ。
ビタミンCを補えるという謳い文句で、
バレンシアオレンジ果汁30%入りの、
独特の沈殿物があるのが特徴だった。
うーん、懐かしい(^^)。
にぎりの一番手は、墨烏賊。
 果たして、旬の名残りの墨烏賊か、
果たして、旬の名残りの墨烏賊か、
旬の走りの墨烏賊か。
昨今、海の中はぐちゃぐちゃで、
漁期も場所も旬もズレズレになってるしー、
スルメ烏賊が全然揚がらないとも聞くしー、
などと思いつつ、うん、美味しい。
お次は、鯛。
 「松野」の大将の煮切り醤油はたっぷりめ。
「松野」の大将の煮切り醤油はたっぷりめ。
鯛はどうやら昆布〆しているようで、
時に愛想のない感じになる鯛がしっとり旨い。
「松野」のガリは甘さはほぼない男前。
油断して口にして、噎せてもーた(^^)。
でも、こんなんも、うん、悪くない。
続いて、巻き海老。
 巻き海老とは、やや小振りな車海老のこと。
巻き海老とは、やや小振りな車海老のこと。
10cm~15cm程度のものをいうらしい。
何気におぼろをかましてくれています。
北寄貝に続いて、赤貝。
 これも旬の名残りというものか。
これも旬の名残りというものか。
うんうん、いーい香りだ。
そして、細魚。
 これもまた春までのタネか。
これもまた春までのタネか。
繊細さの中にある甘さがやっぱりいいね。
お次は、軍艦の雲丹。
 海苔との相性の良さを改めて思う。
海苔との相性の良さを改めて思う。
色味がちょっと浅いのでと訊けば、
その通りのムラサキウニ。
硝子ケースの中にあった下駄の包装紙には、
函館の生産者の名があった。
雲丹は6月からの初夏が旬というイメージだけど、
獲れるところでは獲れる、ってことなのかなぁ。
最近は、明礬臭い雲丹って見掛けなくなったけど、
別の保存方法が開発されたのかなぁ。
そんなことを思ったりもする。
お茶をいただいて、鮪の赤身。
 なんと、昆布〆にしてあると仰る。
なんと、昆布〆にしてあると仰る。
ひと仕事手をかけて美味しく喰わせる。
これぞ江戸前寿司ではないか!
とこっそり膝を打つのであります(^^)。
ガリをちょっぴり齧って、小肌。
 酢〆の酢が甘めなのか、
酢〆の酢が甘めなのか、
煮切りが甘めなのか、甘さを感じる。
うん、こふいふ方向性の小肌も好みだ。
ガスコンロのとろ火で、
さっきまで炙られていた、
穴子がやってくる。
 口に含んだ瞬間にふわっと溶け解れる。
口に含んだ瞬間にふわっと溶け解れる。
うんうん、こうでなくっちゃね。
海苔巻きは、干瓢巻き。

 そして、おきまりひと通りの最後は、玉子巻き。
そして、おきまりひと通りの最後は、玉子巻き。
こんなスタイルの玉子は初めてだ。
海苔の帯で巻く旧来の玉子は見なくなって、
玉子焼きのみというスタイルか、
俗に云う鞍掛けスタイルが、
定番ぽく増えている気がするけど、
こふいふのも面白いね。
トキワ荘通りと並行して、
東長崎から椎名町へと進む大和田通り沿いに、
江戸前「松野寿司」は、ある。
 きりっと気合の入ったお高めな鮨店にも、
きりっと気合の入ったお高めな鮨店にも、
時には伺いたいその一方で、
こんな鮨店が身近な近所にぜひ欲しい。
大将が、仕入れも仕込みも付け台もすべて、
ワンオペで仕事に勤しんでくれているからこそ、
そこに江戸前のひと工夫を添えてくれるからこそ、
安価にこんな小粋なひと時を過ごせるのだと、
その有難さと尊さを想います。
「松野寿司」
東京都豊島区南長崎2-16-12 [Map]
03-3951-3588
