-
 フレンチバル「ランタン・ルージュ」で達郎師匠サンプラザ最終公演の満足感を抱いて
フレンチバル「ランタン・ルージュ」で達郎師匠サンプラザ最終公演の満足感を抱いて
-
 らーめんとかき氷「ねいろ屋」で瀬戸内食材のらーめん女峰のかき氷なははは美味い
らーめんとかき氷「ねいろ屋」で瀬戸内食材のらーめん女峰のかき氷なははは美味い
-
 うなぎ「川勢」でひと通り串焼八幡焼きも焼ひれ焼ばら焼れば焼きも刺えり焼はす焼
うなぎ「川勢」でひと通り串焼八幡焼きも焼ひれ焼ばら焼れば焼きも刺えり焼はす焼
-
 天然水のビール工場「東京・武蔵野ブルワリー」で新プレモルの香りとコクのその訳
天然水のビール工場「東京・武蔵野ブルワリー」で新プレモルの香りとコクのその訳
-
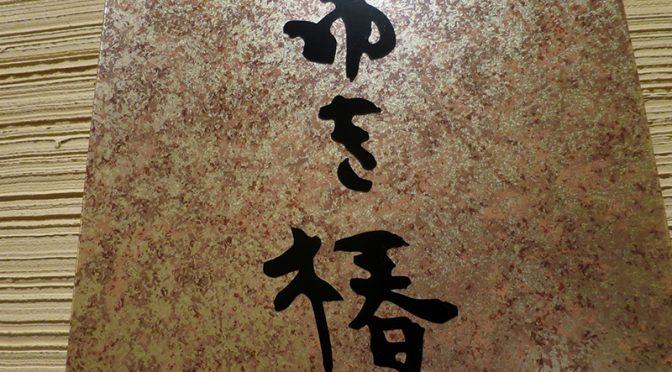 居酒屋「ゆき椿」で栗渋皮揚げ桃白和え秋刀魚肝醤油四面道に大人の居酒屋がある
居酒屋「ゆき椿」で栗渋皮揚げ桃白和え秋刀魚肝醤油四面道に大人の居酒屋がある
-
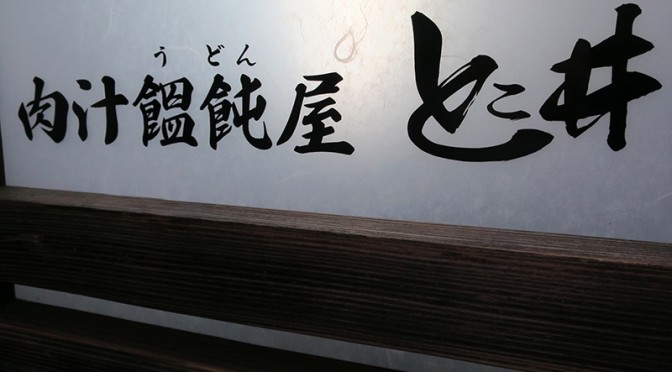 武蔵野うどん専門店「とこ井」で農林61号全粒粉の本手打ち極太麺を具沢山肉汁で
武蔵野うどん専門店「とこ井」で農林61号全粒粉の本手打ち極太麺を具沢山肉汁で
-
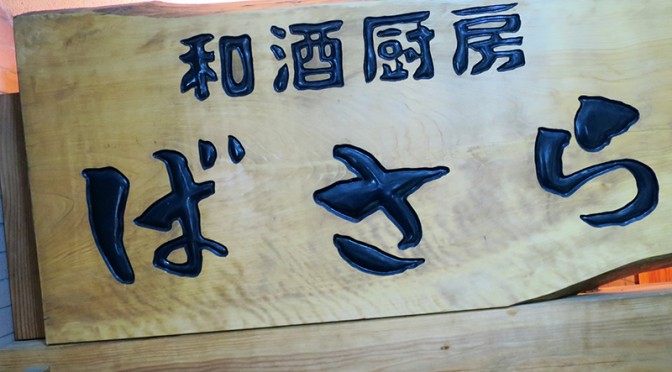 和酒厨房「ばさら」で中央フリーウェイと武蔵野工場見学オトナの遠足のその続き
和酒厨房「ばさら」で中央フリーウェイと武蔵野工場見学オトナの遠足のその続き
-
 自然食居酒屋「やんたけ」で秋の気配新秋刀魚焼霜真鰯梅紫蘇揚特製栗天麩羅に唸る
自然食居酒屋「やんたけ」で秋の気配新秋刀魚焼霜真鰯梅紫蘇揚特製栗天麩羅に唸る
-
 手打ちそばうどん「東小金井 甚五郎」で肉づけ合盛り牡蠣うどん武蔵野うどんDNA
手打ちそばうどん「東小金井 甚五郎」で肉づけ合盛り牡蠣うどん武蔵野うどんDNA
-
 あきる野旬菜果実処「初後亭」で 肉汁もりうどん茹で野菜開店の訳
あきる野旬菜果実処「初後亭」で 肉汁もりうどん茹で野菜開店の訳
-
 SUNTORY PUB「ブリック」で 懐かしのダルマのハイボール
SUNTORY PUB「ブリック」で 懐かしのダルマのハイボール
-
 手打ちそばうどん「国分寺甚五郎」で 今はなき本店と中華そば
手打ちそばうどん「国分寺甚五郎」で 今はなき本店と中華そば
-
 肉汁うどん「夕虹」で 武蔵野台地地産地消真っ当な武蔵野うどん
肉汁うどん「夕虹」で 武蔵野台地地産地消真っ当な武蔵野うどん
-
 うどん処「七」で 肉汁うどん大掻き揚げご自宅系武蔵野うどん
うどん処「七」で 肉汁うどん大掻き揚げご自宅系武蔵野うどん
-
 手打うどん「甚五郎」で 正統派武蔵野うどん蔦覆う店迫る立退き
手打うどん「甚五郎」で 正統派武蔵野うどん蔦覆う店迫る立退き
-
 沖縄料理「きよ香」で 中身イリチー泡盛比べチキアギ在京半世紀
沖縄料理「きよ香」で 中身イリチー泡盛比べチキアギ在京半世紀
-
 炭火焼「鳥久」で ふわり旨い出色れば砂肝から揚げ正しき焼鳥
炭火焼「鳥久」で ふわり旨い出色れば砂肝から揚げ正しき焼鳥
-
 やきとり「いせや」公園店で やきとりホッピー改築前のカウンター
やきとり「いせや」公園店で やきとりホッピー改築前のカウンター
-
 魚料理「らんまん」で 華咲く〆立て鯖浜暴風土佐酢金目の煮付
魚料理「らんまん」で 華咲く〆立て鯖浜暴風土佐酢金目の煮付
-
 焼鳥割烹「川名」で 生グレ牛すじ煮込み大晦日の一献ニッカニカ
焼鳥割烹「川名」で 生グレ牛すじ煮込み大晦日の一献ニッカニカ
