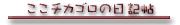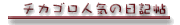それはと或る梅雨入り前の福山駅界隈での思ひ出。
それはと或る梅雨入り前の福山駅界隈での思ひ出。福山駅と云えば、新幹線のホームから間近に城が見えることでも知られている。
まずは、駅のすぐ北側に広がる福山城の広場から城壁沿いをのんびりと辿ってみたりする。
転じて駅の南口はロータリーが整備されていて、植え込まれたチューリップが時期最後の華やかさを映していました。
南口のロータリーを抜けてすぐ。
地場の老舗デパート、天満屋福山店の裏手へ。

 元町通りのアーケードへと繋がる横丁にあるのが、
元町通りのアーケードへと繋がる横丁にあるのが、
おでん洋食「自由軒」だ。
訪れたのはちょうど、正午頃。
 コの字のカウンターを囲む丸椅子。
コの字のカウンターを囲む丸椅子。
そのひとつに止まり木する。
空いていた丸椅子もすぐに埋まってゆく。
中には昼食にと訪れたひともあるやもしれないけれど、
カウンターを囲むほとんどのひとが、
昼呑みモードであります(^^)。
目の前にはゆったりと出汁を湛えるおでん鍋。
その中からまずは「ロールキャベツ」を。

 八丁味噌のような風情の味噌ダレがいい。
八丁味噌のような風情の味噌ダレがいい。
タレの甘味とコク味が、
あっさりと炊いたロールキャベツの魅力を惹き立てています。
「焼酎」に炭酸と檸檬を添えての一杯目。

 壁一面に所狭しと貼り並べられた品書きの札の中に、
壁一面に所狭しと貼り並べられた品書きの札の中に、
「ロールキャベツ」は見つかっても、
例えば「大根」は見当たらない。
「ロールキャベツ」と「スジ」以外のおでんは、
同価格の「おでん」に収斂されているのかもしれません。
幾多の紅い縁取りの品書きの中から、
「自由軒かつ」なる品を探し当てる。
 牛か豚かの串カツかと思えば然にあらず。
牛か豚かの串カツかと思えば然にあらず。
齧って判る、海老と烏賊の串カツで、
それ故、タルタルソースが似合うのであります。
コの字カウンターの中を忙しく動き回っては、
快活な細やかな応対を人懐っこい笑顔で繰り出してくれる、
おばちゃんたちが実に頼もしい。
これだけの品数があり、かつ、
普段暮らす場所と違う土地となれば、
見慣れなず、なんだか判らないメニューに出会うのも、
旅の楽しみのひとつ(^^)。
 「ねぶと唐揚げ」の”ねぶと”とは、
「ねぶと唐揚げ」の”ねぶと”とは、
瀬戸内の小魚、天竺鯛のことらしい。
サクサクと軽やかにいただけて、
どんどん食べてしまいます。
お隣のオヤジさんの註文を真似して、
「Aセットお願いします」とオーダーする。
 そうして手にしたのは、
そうして手にしたのは、
チロリに入った1合程の焼酎と缶のウーロン茶、
そして氷入りのグラスの3点セット。
そう、これで自分でウーロンハイを作るのだ。
お手製のウーロンハイをちびちびしながら、
「キモテキ」を摘まむ。
 トンテキが豚のステーキならば、
トンテキが豚のステーキならば、
「キモテキ」は、豚レバーのステーキ。
部分的に揚げ焼いたようにもなっていて、
そこに下町の洋食屋的ソースがかかっている。
これももまた、酒のあてにも飯のおかずにもなる逸品だ。
「ポテトサラダ」で最後の一杯を飲み干そうとする頃、
「オムライス」がやってきた。

 量感たっぷりにして、
量感たっぷりにして、
正しき昭和のニッポンのオムライスの佇まいにまず満足する。
おでんと定食の大衆食堂的気安さと、
洋食の老舗としての気風が交叉しているようで、
美味しくも頼もしく映るのであります。
福山駅南口、天満屋福山店の裏手に、
創業1951年(昭和26年)のおでん洋食「自由軒」はある。
 ほろ酔いのまま店内から暖簾を潜り出れば、
ほろ酔いのまま店内から暖簾を潜り出れば、
おばちゃんたちに元気をもらったことにふと気づく。
今は夕方からの営業に変更されているようです。
「自由軒」
広島県福山市元町6-3 [Map]
084-925-0749