-
 シチリア料理「L’ottocentoロットチェント」で浅草開化楼と掛け算わしわしイタリアン
シチリア料理「L’ottocentoロットチェント」で浅草開化楼と掛け算わしわしイタリアン
-
 肉そば肉うどんのお店「南天」本店で肉うどん椎名町駅北口の味お巡りさん御用達
肉そば肉うどんのお店「南天」本店で肉うどん椎名町駅北口の味お巡りさん御用達
-
 餃子専門店「中央亭」で大中小焼いて茹でる餃子の旨さに裏を返す
餃子専門店「中央亭」で大中小焼いて茹でる餃子の旨さに裏を返す
-
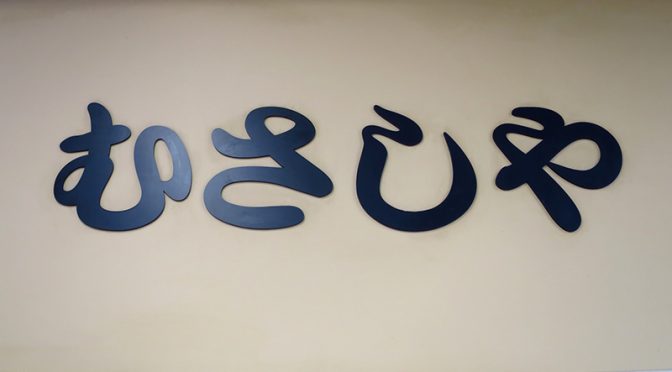 洋食スタンド「むさしや」で定番ナポにオムライスハンバーグ丼にカレースパもいい
洋食スタンド「むさしや」で定番ナポにオムライスハンバーグ丼にカレースパもいい
-
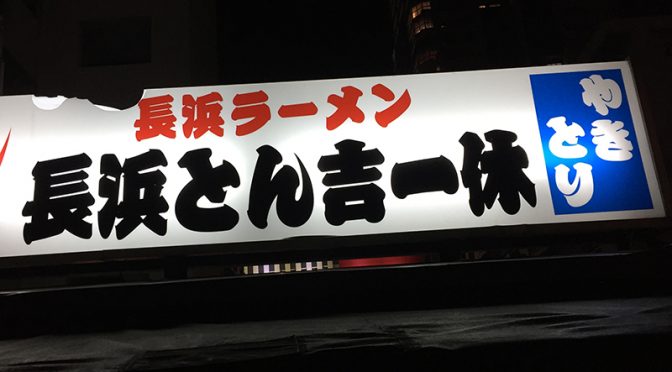 長浜屋台「長浜とん吉一休」でご無沙汰の屋台街の静けさに焼酎お湯割り〆のラーメン
長浜屋台「長浜とん吉一休」でご無沙汰の屋台街の静けさに焼酎お湯割り〆のラーメン
-
 おでん・たいやき「にしみや商店」で 出汁の無垢な正しさ天然物鯛焼
おでん・たいやき「にしみや商店」で 出汁の無垢な正しさ天然物鯛焼
-
 名物焼だんご「武蔵屋」で 炭火の焦げと醤油の郷愁道灌団子
名物焼だんご「武蔵屋」で 炭火の焦げと醤油の郷愁道灌団子
-
 元祖串かつ「だるま」で 見上げる通天閣揚立て旨し元祖串かつ
元祖串かつ「だるま」で 見上げる通天閣揚立て旨し元祖串かつ
-
 所沢名物焼だんご「奈美喜屋」で 焼き立て湯気と醤油の芳ばしさ
所沢名物焼だんご「奈美喜屋」で 焼き立て湯気と醤油の芳ばしさ
-
 そば処「狭山そば」で ホームで立ち食い天玉そばずっとそのまま
そば処「狭山そば」で ホームで立ち食い天玉そばずっとそのまま
-
 Bosna「Balkan Grill Walter」で カレー粉塗しソーセージのボスナ
Bosna「Balkan Grill Walter」で カレー粉塗しソーセージのボスナ
-
 お好み焼き「甚六」で かき玉お好み焼そばアーケードの向こう側
お好み焼き「甚六」で かき玉お好み焼そばアーケードの向こう側
-
 包子餃子「スヰートポーヅ」で 素朴に旨い餃子天津包子水餃子
包子餃子「スヰートポーヅ」で 素朴に旨い餃子天津包子水餃子
-
 お好み焼き「松浪」で 松浪浪速芳町焼きかきバター醤油の匂い
お好み焼き「松浪」で 松浪浪速芳町焼きかきバター醤油の匂い
-
 トンコツ焼きそば「じゅうはち」で さっぱりもとい限定濃厚トンコツ
トンコツ焼きそば「じゅうはち」で さっぱりもとい限定濃厚トンコツ
-
 餃子専門店「東京餃子楼」で実直な焼き餃子水餃子もやし大ヒット
餃子専門店「東京餃子楼」で実直な焼き餃子水餃子もやし大ヒット
-
 スパゲティハウス「そ~れ」で あんかけスパそ~れ嗚呼油まみれ
スパゲティハウス「そ~れ」で あんかけスパそ~れ嗚呼油まみれ
-
 たこ焼「築地 銀だこ」中延店で 薄クリスピーとろろんクリーミー
たこ焼「築地 銀だこ」中延店で 薄クリスピーとろろんクリーミー
-
 鉄板焼「一」で ふるふるゆるゆる牛すじ定食貝割れ白髪葱
鉄板焼「一」で ふるふるゆるゆる牛すじ定食貝割れ白髪葱
-
 スパゲッティ「ジャポネ」で 敢えてポークカレーはへそ曲がり
スパゲッティ「ジャポネ」で 敢えてポークカレーはへそ曲がり
