-
 フレンチバル「ランタン・ルージュ」で達郎師匠サンプラザ最終公演の満足感を抱いて
フレンチバル「ランタン・ルージュ」で達郎師匠サンプラザ最終公演の満足感を抱いて
-
 OSTERIA ENOTECA「ダ・サスィーノ」で弘前城の桜と自ら育む食材自家製ワイン
OSTERIA ENOTECA「ダ・サスィーノ」で弘前城の桜と自ら育む食材自家製ワイン
-
 普段着フレンチ「La mignonnette」でさくら通りとオニグラロールキャベツと
普段着フレンチ「La mignonnette」でさくら通りとオニグラロールキャベツと
-
 海辺ダイニング「Funny Dining HAYAMA」でテラスにて車海老タルタル葉山牛
海辺ダイニング「Funny Dining HAYAMA」でテラスにて車海老タルタル葉山牛
-
 Weinstube「AndreasHofer」で石畳の小路シュタインガッセ辿る古き良き郷土料理店
Weinstube「AndreasHofer」で石畳の小路シュタインガッセ辿る古き良き郷土料理店
-
 BISTRO「Roven」が八丁堀にやってきたデミグラスのロールキャベツにドライカレー
BISTRO「Roven」が八丁堀にやってきたデミグラスのロールキャベツにドライカレー
-
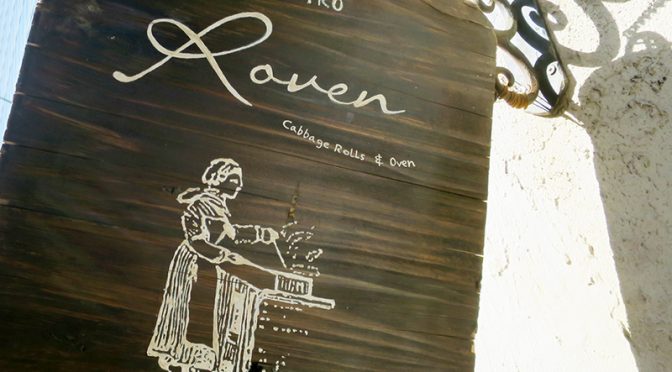 BISTRO「Roven」で彩り三種のロールキャベツにハンバーグ気になるファサード
BISTRO「Roven」で彩り三種のロールキャベツにハンバーグ気になるファサード
-
 TAVERN「POSTSTUBE 1327」でトラウン湖の風光エッゲンベルグとグーラッシュ
TAVERN「POSTSTUBE 1327」でトラウン湖の風光エッゲンベルグとグーラッシュ
-
 Restaurant「Domaine de Mikuni」で蝦夷鮑ヴルーテ夏鱈炙り焼き追分の別荘地にて
Restaurant「Domaine de Mikuni」で蝦夷鮑ヴルーテ夏鱈炙り焼き追分の別荘地にて
-
 レストラン「キッチン カントリー」でハンガリー料理の息吹自由が丘デパートに
レストラン「キッチン カントリー」でハンガリー料理の息吹自由が丘デパートに
-
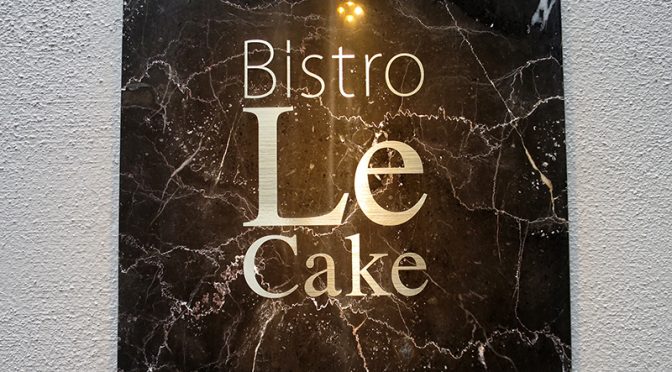 Bistro「Le Cake」でケイクサレ添えサラダにアッシパルマンティ灯りまたひとつ
Bistro「Le Cake」でケイクサレ添えサラダにアッシパルマンティ灯りまたひとつ
-
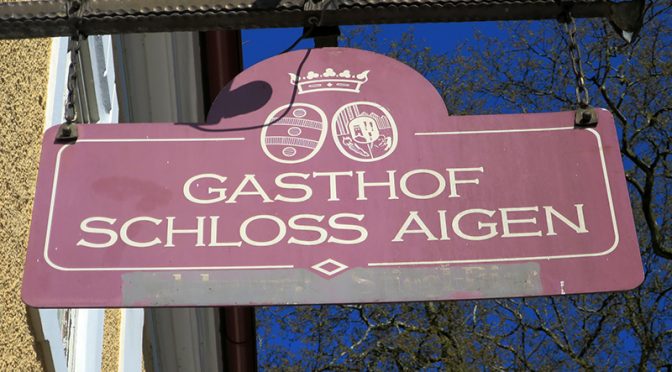 GASTHOF「SCHLOSS AIGEN」でフィレ肉タルタルパイクパーチのメダイヨン
GASTHOF「SCHLOSS AIGEN」でフィレ肉タルタルパイクパーチのメダイヨン
-
 Restaurant「BÄREN WIRT」で包み揚げシュパーゲルにレバー版シュニッツェル
Restaurant「BÄREN WIRT」で包み揚げシュパーゲルにレバー版シュニッツェル
-
 「KOHLMAYR’S GAISBERG SPITZ」で山頂ブランチ眼前の超絶大パノラマにああ凄い
「KOHLMAYR’S GAISBERG SPITZ」で山頂ブランチ眼前の超絶大パノラマにああ凄い
-
 Brasserie「Gyoran」で蝦夷鹿赤ワイン煮鴨肉コンフィ仔牛カツレツ牛ハラミ肉に満足
Brasserie「Gyoran」で蝦夷鹿赤ワイン煮鴨肉コンフィ仔牛カツレツ牛ハラミ肉に満足
-
 江戸前ビストロ「EDOGIN」で青唐辛子ハチビキ海老クリコロと海のワインVIONTA
江戸前ビストロ「EDOGIN」で青唐辛子ハチビキ海老クリコロと海のワインVIONTA
-
 Restaurant 「STRASSE WIRT」で絶品シュパーゲルスープと仔牛の膵臓への魂胆
Restaurant 「STRASSE WIRT」で絶品シュパーゲルスープと仔牛の膵臓への魂胆
-
 Restaurant「BÄREN WIRT」でAugustinerのジョッキSpargel揚焼きBÄRENは熊印
Restaurant「BÄREN WIRT」でAugustinerのジョッキSpargel揚焼きBÄRENは熊印
-
 BISTRO「サンシビリテ」で仔羊の背肉香草風味と青森産バルバリー鴨ローストの夜
BISTRO「サンシビリテ」で仔羊の背肉香草風味と青森産バルバリー鴨ローストの夜
-
 メインダイニング「THE FUJIYA」で継承してきたことを丁寧に供する感じがいい
メインダイニング「THE FUJIYA」で継承してきたことを丁寧に供する感じがいい
