-
 炭火焼とり「羅生門」で煮込みポテサラしのえ焼き二葉橋高架下トンネルの暗がりは今
炭火焼とり「羅生門」で煮込みポテサラしのえ焼き二葉橋高架下トンネルの暗がりは今
-
 SPAGHETTERIA「Hungry Tiger」でやはりダニエルそしてバジリコワシワシ麺がいい
SPAGHETTERIA「Hungry Tiger」でやはりダニエルそしてバジリコワシワシ麺がいい
-
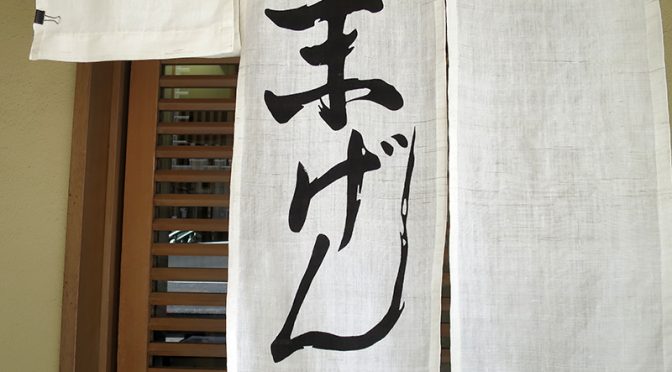 鳥割烹「末げん」で老舗の風格滲むかま定食何れがから揚げかたつた揚げか
鳥割烹「末げん」で老舗の風格滲むかま定食何れがから揚げかたつた揚げか
-
 蕎麦處「大坂屋 砂場 本店」で高層ビルと登録有形文化財老舗の安定感を思う蕎麦
蕎麦處「大坂屋 砂場 本店」で高層ビルと登録有形文化財老舗の安定感を思う蕎麦
-
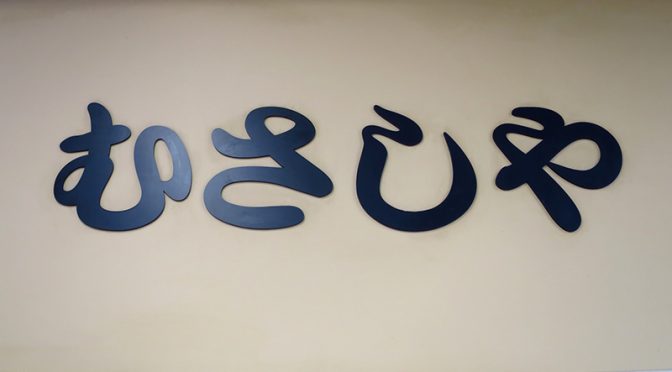 洋食スタンド「むさしや」で定番ナポにオムライスハンバーグ丼にカレースパもいい
洋食スタンド「むさしや」で定番ナポにオムライスハンバーグ丼にカレースパもいい
-
 ホルモン「在市」芝大門で旨い赤身肉とホルモンのごちゃ混ぜ焼きとジントニと
ホルモン「在市」芝大門で旨い赤身肉とホルモンのごちゃ混ぜ焼きとジントニと
-
 とんかつ「燕楽」でカツ丼カツカレーロースカツ定食あの頃の溢れる活気と朗らかさ
とんかつ「燕楽」でカツ丼カツカレーロースカツ定食あの頃の溢れる活気と朗らかさ
-
 炭の屋「でですけ」で炭焼き鯖串にレバー串日本固有品種の赤マスAが良く似合う
炭の屋「でですけ」で炭焼き鯖串にレバー串日本固有品種の赤マスAが良く似合う
-
 江戸前ビストロ「EDOGIN」で青唐辛子ハチビキ海老クリコロと海のワインVIONTA
江戸前ビストロ「EDOGIN」で青唐辛子ハチビキ海老クリコロと海のワインVIONTA
-
 Oyster Bar「ジャックポット」汐留であれこれ牡蠣と海のワインVIONTA
Oyster Bar「ジャックポット」汐留であれこれ牡蠣と海のワインVIONTA
-
 沖縄料理と島酒「琉球食堂」でしりしりクープ春巻沖縄担々麺沖縄風ちゃんぽん
沖縄料理と島酒「琉球食堂」でしりしりクープ春巻沖縄担々麺沖縄風ちゃんぽん
-
 PUBLIC BAR「雑魚」で 〆鯖ガリ和え目光唐揚鰯二度殺し酒盗ピザ
PUBLIC BAR「雑魚」で 〆鯖ガリ和え目光唐揚鰯二度殺し酒盗ピザ
-
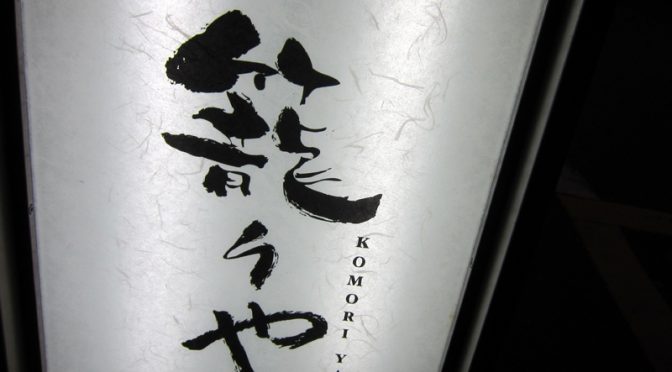 和食居酒屋「籠りや」で 肌理泡の表情眺めるプレモル超達人店
和食居酒屋「籠りや」で 肌理泡の表情眺めるプレモル超達人店
-
 つけ麺中華そば「月と鼈」で 煮干し中華そば一段搾り煮干し増し
つけ麺中華そば「月と鼈」で 煮干し中華そば一段搾り煮干し増し
-
 喫茶室「ポワ」で 思い出して食べたくなるナポリタン店の名は豆
喫茶室「ポワ」で 思い出して食べたくなるナポリタン店の名は豆
-
 Oyster Bar「Jack Pot」汐留で かき会議三陸の牡蠣をいただく
Oyster Bar「Jack Pot」汐留で かき会議三陸の牡蠣をいただく
-
 Restaurant「ケルン」で 魅力的的矢生牡蠣とカキフライに思うこと
Restaurant「ケルン」で 魅力的的矢生牡蠣とカキフライに思うこと
-
 魚の旨い店「和楽」で 昼尚入れ込み居酒屋のかきフライ定食
魚の旨い店「和楽」で 昼尚入れ込み居酒屋のかきフライ定食
-
 餃子食堂「ネヂ」で 酒肴に真っ直ぐ焼餃子生餃子ハギ肝タコの子
餃子食堂「ネヂ」で 酒肴に真っ直ぐ焼餃子生餃子ハギ肝タコの子
-
 芝大門「麺や ポツリ」で濃厚煮干しつけ麺中華そばセンスを思う
芝大門「麺や ポツリ」で濃厚煮干しつけ麺中華そばセンスを思う
