-
 スタンディング「8オンス」で白州18年ハイボール松本城の濠の上時空を越えて
スタンディング「8オンス」で白州18年ハイボール松本城の濠の上時空を越えて
-
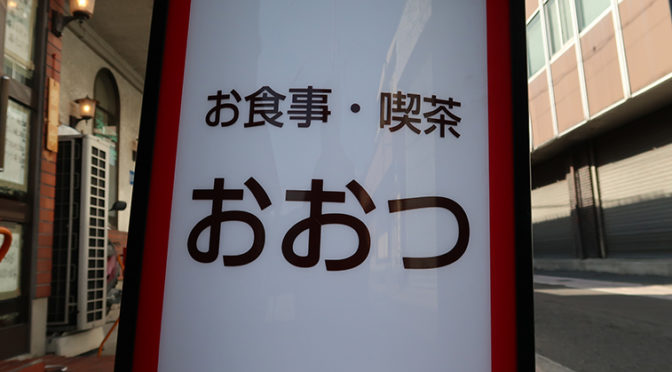 グリル「おおつ」で見栄え麗しきカツカレーよく炒めナポあれば生姜焼きもある
グリル「おおつ」で見栄え麗しきカツカレーよく炒めナポあれば生姜焼きもある
-
 御そば打處「野麦」で端正な面持ちのざるの蕎麦五種の具の淡々と旨いかけの蕎麦
御そば打處「野麦」で端正な面持ちのざるの蕎麦五種の具の淡々と旨いかけの蕎麦
-
 Restaurant「Domaine de Mikuni」で蝦夷鮑ヴルーテ夏鱈炙り焼き追分の別荘地にて
Restaurant「Domaine de Mikuni」で蝦夷鮑ヴルーテ夏鱈炙り焼き追分の別荘地にて
-
 純手打ちそば「奥村本店」で登美の丘ワイナリーの葡萄畑そこがゆえの日本ワインたち
純手打ちそば「奥村本店」で登美の丘ワイナリーの葡萄畑そこがゆえの日本ワインたち
-
 味処「きく蔵」で大雪渓と特上馬刺しおやき的名物筍饅頭つらら麺松本の宵の口
味処「きく蔵」で大雪渓と特上馬刺しおやき的名物筍饅頭つらら麺松本の宵の口
-
 カレーの店「デリー」で蔵のある町の黒塗りの蔵にあの有名店の看板を見付けたら
カレーの店「デリー」で蔵のある町の黒塗りの蔵にあの有名店の看板を見付けたら
-
 蕎麦処「源智のそば」で擂鉢の荏胡麻が引き立てる笊蕎麦の美味しさ名水の傍らで
蕎麦処「源智のそば」で擂鉢の荏胡麻が引き立てる笊蕎麦の美味しさ名水の傍らで
-
 中華そば「杭州飯店」で燕三条背脂らーめん元祖と謳われるどんぶりに風格想う
中華そば「杭州飯店」で燕三条背脂らーめん元祖と謳われるどんぶりに風格想う
-
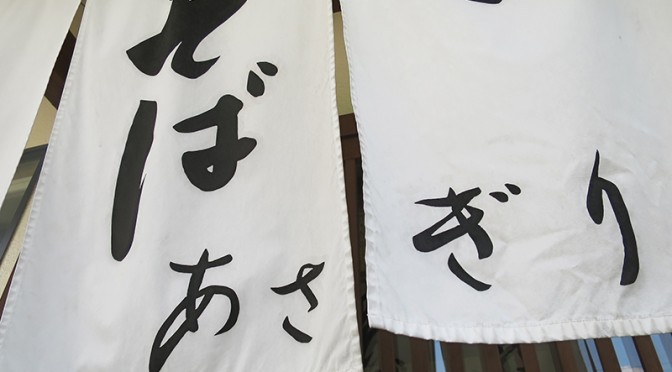 手打そばうどん「あさぎり」でゆっくりおひるの鴨せいろ北軽井沢嬬恋のひと時
手打そばうどん「あさぎり」でゆっくりおひるの鴨せいろ北軽井沢嬬恋のひと時
-
 薪窯ピザ「enboca軽井沢」で大葉ちりめん山椒無花果に桃のピザ再会の初夏のテラス
薪窯ピザ「enboca軽井沢」で大葉ちりめん山椒無花果に桃のピザ再会の初夏のテラス
-
 純手打生蕎麦「奥藤 本店」で鳥もつ煮発祥の蕎麦の店信玄公像と舞鶴城公園の桜と
純手打生蕎麦「奥藤 本店」で鳥もつ煮発祥の蕎麦の店信玄公像と舞鶴城公園の桜と
-
 手打生そば「かぎもとや」本店で 安い燗酒と野趣のそばゆるゆる
手打生そば「かぎもとや」本店で 安い燗酒と野趣のそばゆるゆる
-
 Restaurant「エルミタージュ ドゥ タムラ」で 軽井沢和みの隠れ家
Restaurant「エルミタージュ ドゥ タムラ」で 軽井沢和みの隠れ家
-
 中国風菜館「萬里」で 伊那地方特有の麺料理ローメン発祥の店
中国風菜館「萬里」で 伊那地方特有の麺料理ローメン発祥の店
-
 Bar「Hakushu」で 白州25年素直な余韻と森の蒸溜所の休日
Bar「Hakushu」で 白州25年素直な余韻と森の蒸溜所の休日
-
 フードコート「Cu-Cal」×イタリア料理 「イル・ギオットーネ」
フードコート「Cu-Cal」×イタリア料理 「イル・ギオットーネ」
-
 釜焼ピザ「enboca」で 想定外の満足ピザ口から口へああ旨い
釜焼ピザ「enboca」で 想定外の満足ピザ口から口へああ旨い
-
 西洋料理「明治の館」で ビールと特製ソーセージとオムライスと
西洋料理「明治の館」で ビールと特製ソーセージとオムライスと
-
 手打生そば「かぎもとや」バイパス塩沢店で 天ざる山うどの香り
手打生そば「かぎもとや」バイパス塩沢店で 天ざる山うどの香り
